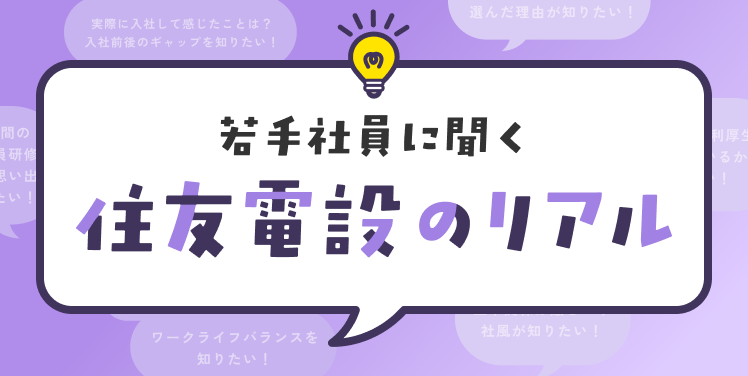interview
建物に初めて照明が灯る。
その感動は、忘れられない。
I.Y.
- 部門
- 東京支社
- 勤務地
- 東京

現在のお仕事内容を教えてください。
主にホテルや研究所等のテナントビルの新築工事に伴う電気設備の施工管理を行っています。現在の担当案件では、更地の段階から現場に入り、漏電時に電気を逃がすためのアース接地工事や、建物の基礎に配管を通すための貫通穴スリーブ工事について、一連の現場管理を任されています。具体的には、事故災害を防止するための安全管理、工事の進捗に応じた施工確認や検査書類の作成等の品質管理、電気の送電等を行っています。
また建物が竣工を迎えてからも、テナント工事で新しく照明器具やコンセントを追加することもあります。さらに年に一度、竣工後の建物に異常がないかを確認する電気設備年次点検も行っています。
職場の雰囲気はいかがですか?
入社前は、現場でのコミュニケーションに不安があったのですが、実際には心配することは全くありませんでした。作業員の方々はみなさんとても気さくで、困ったときやわからないことがあれば、親身になって教えてくださいます。基本的には、どの現場も作業員の方々と一丸になって仕事を進めていく必要があるので、コミュニケーションはとても大切です。ほとんどの場合、初対面かつ年上の方が多いので、あいさつは元気よく、積極的に話しかけるように心がけています。

最もやりがいを感じるのは、どういったときですか?
やはり現場が受電を迎え、建物に電気が灯る瞬間です。1~3年目は搬入や施工の確認などで現場内を行き来することが多く、忙しい時期は大変なこともありますが、初めて建物に照明が灯る瞬間の感動は忘れられません。最初に担当した現場はホテルだったのですが、薄暗かった廊下に一列に並んだ照明がいっせいに点灯するのは、とてもきれいでした。
また、4年目以降は現場代理人として施主やテナントの方と打ち合わせを行う機会も増えてきます。照明の配置などは設計図ですでに定められているのですが、特にテナント工事では内装に大きく影響するので、照明の種類や配置について直接ご相談いただくことも多いです。私も最近照明計画を作成する機会が増えてきたところなのですが、自分の描いた図面が実際の現場に反映されていくのは感慨深いです。お客様のご要望を受けて、コスト的にもデザイン的にもベストな施工をご提案できたときは、とてもうれしいですね。
今後の目標・展望についてお聞かせください。
いずれは誰もが知るようなテーマパーク等の大きな物件を担当したいです。建物の規模が大きくなるにつれて、安全管理や品質管理だけではなく、電気的に理解しないといけないことが増えてくるため、資格がなければ担当できない現場も多々あります。大変だとは思いますが、将来的には大きな物件の施工に携わり、自分の子供に自慢できたらと思います。実は、私の父も電気に携わる仕事をしていたんです。父が施工した物件を実際に見て子供ながらにとても感動したことを、今でも覚えています。

flow 一日の流れ
-
- 通勤
- 好きな音楽を聴きながら電車で通勤。
-
- 出社・朝礼
- 作業員とその日の施工内容、施工場所に応じて危険ポイントを確認。一日の現場の流れを周知する。
-
- 現場巡回
- 当日の作業場所の確認。作業エリアは班ごとに分かれるので、進捗に合わせて現場を確認する。
-
- 小休憩
- 作業員と詰所で翌日の作業内容や工程を確認し、調整を行う。事務所に戻り資材発注。
-
- 昼礼
- 現場全体の進捗と翌日の作業内容を建築・設備業者の各職長と確認。調整を行う。
-
- 昼食
- 基本的には現場事務所で職員皆と食事。
-
- 現場巡回
- 午後からの変更事項や現場全体としての周知事項を作業員さんと確認する。
-
- 施工確認
- 指示した図面と現地との整合がとれているかをチェックする。
-
- 事務作業
- 事務所に戻り、撮影した施工写真を工事項目ごとに台帳にまとめ、検査書類を作成する。
-
- 現場巡回
- 進捗状況と現場の終わり仕舞いを確認する。作業員さんと翌日以降の作業内容を打ち合わせ。
-
- 事務作業
- 図面の作図や施工計画書の作成、翌日の作業内容を確認する。
-
退社
-
- 帰宅
- 夕食や入浴、テレビの時間。
-
就寝